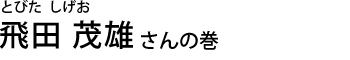  |
| |||||||||||||||||
◇「こちらに『土佐一』、それから『それから』。お湯割りでね」 酒をこよなく愛する飛田氏のインタビューは、氏のなじみの店で行なわれた。品書きには、他ではなかなか見られない銘柄の日本酒などがずらりと並ぶ。つまみも気の利いた品ばかりで、しかも気取らない。酒好きにはたまらない、さすがの店選びである。そして酒にちなんだエピソードには、往年の名翻訳者の名前がこれまたずらりと登場する。「翻訳者や出版社の人ともよく飲みましたね。大久保(大久保康雄氏)・田中(田中西二郎氏)の両氏とはあまり飲まなかったけれど、橋本(橋本福夫氏)さんとは何かにつけて新宿を飲み歩きましたよ。あの方からは、ずいぶん影響を受けました。翻訳そのものについて習ったことはないけれど、文学とか、自然とか、人間とかを本当に愛しているという意味で、心を打たれるものがあったんです。いい人だなぁ・・・・・・と」 翻訳をするときには、お酒は?「若いころは、夜、したたか飲んでからやっていましたね。できなくなったのは、65歳を過ぎてから。眠くなっちゃう」 もっとも朝が遅いからできたことですが、と飛田氏は笑ってお気に入りの焼酎のグラスを傾けた。「ろばに乗られた」?飛田氏と翻訳との出会いは、大学を出た年のこと。エドガー・J・グッドスピードの英訳聖書『ショート・バイブル』を日本語へ重訳するというものであった。それも、文人宰相として名高く、敬虔なクリスチャンでもあった片山哲氏の代訳である。「天職」を英語でcalling――つまり、「神からのお声掛かりでする仕事」――というように、氏の天職ともいえる翻訳とのめぐりあわせは、まさに神が取り持つ縁だったといえる。 「友人ふたりと一緒だったんですが、のめりこんで訳しました。聖書の魅力、つまり『人間』イエスの、いわば宗教革命家としての命がけの努力に感動したんです。それから、当時の聖書には、教会用語ともいうべき独特の言いまわしや奇妙な敬語づかいが多かったので、違和感のない日本語に訳すという取り組みに力を入れました。『イエスはろばに乗られた』なんて言い方がありますが、まるでイエスがろばの下敷きになったみたいに聞こえるじゃないですか(笑)。地の文で敬語を使わなかった聖書は、我々のものが最初だったんじゃないかな」 翻訳とはこういうものだ、ということを意識するよりも、いい日本語にしたいという一心で訳したという。本代ほしさの翻訳修行その後大学院へ進んだ氏は、意気投合した友人とふたりでE・M・フォースターの小説をふたつ訳してみた。それは純粋に作品に対する愛着と、作家に対する興味からであり、翻訳をやりたかったからでも、出版の意図があったわけでもない。しかしある日、どうしたはずみかプロの翻訳者に見てもらおうという話になった。 「アポも取らずに『白鯨』の翻訳で有名な田中西二郎氏のところへ押しかけたんです。そうしたら、なぜかわかりませんが、わたしを代訳に使いたい、と」 代訳とは文字どおり、代わりに訳すこと。つまりは飛田氏の訳した文章が、田中氏の名前で世に出るのである。しかも、下訳とは違って直しはまったく入らない。いかに当初から飛田氏の英語力、表現力がすぐれていたかが伺い知れるエピソードだ。さらには田中氏の紹介で、黒人文学に造詣の深いアメリカ文学者でありながら、クリスティの翻訳(ハヤカワ・ミステリ文庫)なども多数ものした橋本福夫氏や、『風と共に去りぬ』(新潮文庫)やホームズもの(ハヤカワ・ミステリ文庫)などを手がけた大久保康雄氏の代訳や下訳にも抜擢される。ときに飛田氏は20代の青年であり、翻訳を生業とするには幸先のいいスタートを切ったことになる。それなのに――「翻訳者になるなんてことは考えていませんでした。大学院に行っていましたから、大学の教員になろうとしていたわけです。ですから翻訳でおこづかいを稼げば、本が買えて論文が書ける、そんなふうに思っていたんですね」 しかし当時は、「代訳者をいずれは独立させてやろう、という親切さがあった」(飛田氏)。やがて大久保氏の後押しで、昭和40年に初めて氏の名前を冠した訳書――パール・バックの『母の肖像』――が出ることになる。これで名実ともに翻訳者・飛田茂雄が誕生したというわけだ。またこの頃、氏は最初に教員職を得た青山学院大学から北海道の小樽商科大学へと転任し、助教授となっていた(その後中央大学教授となり、帰京)。当時は地方にいる翻訳者が、都内の出版社から仕事を頼まれることなど極めてまれな時代。そうしたいわば不利な環境にありながらも、氏のもとには、早川書房の編集者であったあの常盤新平氏からのオファーを初めとして、生真面目で翻訳の難しい作品ばかりが持ち込まれるようになり出した。 「エンターテイメント性のあまり高くない作品を第一作として出しましたから、そういうものが得意だという印象を与えたのでしょう。あてがわれる作品は決まって訳しにくいものばかり。なぜ常盤さんがわたしを選んでくれたのか、これもまたわからないんですが、とにかく手探り状態での翻訳作業でした。いいスラングの辞書もない時代ですから、学内にたった一人の外国人講師を頼りにしたり、せっせと著者に手紙を書いて質問したり。著者からの返事は結構くるもので、こなかったのはふたりだけですね。手紙のやりとりで非常に親しくなれたのはヘンリー・ミラーです。会う機会はありませんでしたが・・・・・・。」 こうして与えられるままに仕事をこなす日々が続いたが、着実な仕事ぶりを評価されるなか、次第に氏の意見も取り入れられるようになっていく。氏の手がけた本のジャンルは純文学から神話学、美術書と多岐に渡るが、取捨選択のポイントはどこにあるのだろうか。「大学の教員ですから、嫌なものは『大学があるから』と断ればいいんです(笑)。逆に『これはぜひ訳させて欲しい』と無理をいったこともあります。神話学者ジョーゼフ・キャンベルの『神話の力』がそうですね。これらはいまでも非常に気に入っていますし、何度でも読む価値がある本だと思います。断るときは、まったく率直にいいます。浅薄なものはやりたくないですね。おもしろくない、深みがない、2度読む気がしない、そういうものはやりたくありません」 『ショート・バイブル』やフォースターの訳の時代から連綿と続く、氏を翻訳作業へと駆り立てる原動力――それは作品と作者に対する愛着なのだということが、再確認できる言葉ではないだろうか。翻訳の副産物――辞書批評飛田氏は、小学館『ランダムハウス英語辞典』の初版発行に協力したのを皮切りに、以後30年もの長きに渡って辞書の改善・改良に力を尽くしている。辞書の執筆者に名を連ねるところから始まって、『役に立つ辞書を探す本』(バベル・プレス)、『わたしが愛する英語辞典たち』(南雲堂フェニックス)、『探検する英和辞典』(草思社)、『いま生きている英語』(中公新書)、『現代英米情報辞典』(研究社出版)にいたるまで、辞書に関する著書や、それ自体が辞書として使える著書も多く、辞書の質向上のためには常に問題提起を怠らない。 「(辞書は)ずいぶんよくなりましたよ。率直に批判する人が出てきたからです。けれども完璧からはほど遠い。完璧はありえませんしね」 かつては英語学や英米文学を研究している大学の教員が、辞書に注文をつけたり批判したりすることはタブー視されていたという。そうしたなか、あえて批判の声をあげたことで、どんな反応があったのだろうか。「おまえさんは夜の神保町をひとりでは歩けないよ、とおどかされました(笑)。でも実際は、表立った反論は何もありませんでした。逆に辞書編纂の第一人者から講演を頼まれたりして・・・・・・批判されたほうも納得していたんじゃないですか。誰が見てもおかしいのは間違いないですから。そういう意味では、先陣を切ったといえるでしょうね。怖いものしらずだったんです。学閥の出身じゃないから、しがらみもないし」 氏の熱意とたゆまぬ取り組みがあってこそ、いま、わたしたちはすぐれた辞書の恩恵を受けることができるのだ。押してもだめなら引いてみな――翻訳は想像力が勝負教員として翻訳論を教え、翻訳者として苦労して訳文をつくる。だから常に「どこを勉強するべきか」を考えているという。 「結論からいえば、想像力しかないんです。想像力の限界は、3歳くらいまでに決まってしまうという説もあるけれど、伸ばす方法はあると思っています。ものごとを、裏から表から、右から左から見るんです。押してもだめなら引いてみな、と発想を転換する――そうすれば多少はマシになる」 翻訳は、人間の想像力が試される場でもあるのだ。「ヘミングウェイの『殺し屋』という作品で、殺し屋が田舎町の食堂の主人に質問をする。それを字面どおりに読めば『えれえ景気のいい町じゃねぇか』です。つまり、皮肉なんですね。本当はつまらない町なんだけど、景気がいいねと皮肉をいっている。でも、どの翻訳も、のきなみ『しけた町』と訳しているんだな。これはもう人のまねをしているか、言葉を知らないとしか思えないでしょう。皮肉は皮肉として訳さないと面白味がないのに。想像力がないんです。ただ英語がわかればいいってもんじゃないんですよ」 このあたりに興味のある方は、氏の『翻訳の技法』(研究社出版)をぜひご一読あれ。真摯に、謙虚に、たゆみなく翻訳を勉強したことのある人なら、表現に凝ったり、うまい言い換えをしようと色気を出したりして、かえって失敗した経験があるだろう。かの柴田元幸氏がいつもいっているように、翻訳者は黒衣に徹すること、読者に対する愛情と、作家に対する惚れ込みがあって、やっと翻訳ができるのだ――と飛田氏は強調する。 「自分を出そう出そうとする翻訳じゃなくて、抑えよう抑えようとする気持ちを持って翻訳をする。自分を抑えながら、読者のためにサービスをするんです。自分の知っていることを全部盛り込もうというような、過剰なサービスは逆効果ですから、ほどのよさを会得していくことです」 そして翻訳の修行にしろプロとして仕事をするにしろ、数年、あるいは十数年単位の長い時間をかけた取り組みを厭わない態度が大切だ。「わたしの頃は、下訳や代訳を7、8年やるなんていうのは当たり前の時代でね。いまの人たちは1年半たてば一人前になれると思っているし、なれなきゃ嫌なんだ。確実性を求めたり、結果を求めたりして、辛抱がない。名前を出したい、答えを出したい、とね。それでいてある段階で難しい問題にぶつかると、すぐ『先生お願いします』とくる」 疑問に突き当たってから3年たったある日の古本屋で、突然答えにめぐりあうことだってある。その喜びを知らないなんて哀れだし、甘ったれている――それまで一貫して穏やかだった氏の語り口に、熱いものが感じられた。「ジョーゼフ・ヘラーの『キャッチ=22』を訳すとき、作品に何度もB-25爆撃機が出てきたのですが、構造がよくわからない。そこでB-25のプラモデルを買い、1カ月かけて組み立てた。でも中の構造なんてプラモデルじゃわかりゃしなくてね(笑)。本物を見たのは、それから10数年後、ミネソタの公園でです。作品では、距離にすればほんの3メートル程度の通路を、非常に長い時間をかけて通ってきたように書かれていた。つまり、ほんの短い距離を長いもののように誇張して書くことで、戦争という異常事態のもとで追い詰められた主人公の精神を表していた点にやっと気づいた。そういうこともあるんです」 大学で研究者としての道を究めつつ、さまざまなジャンルを手がける翻訳者として50年近いキャリアを積み上げてきた飛田氏。翻訳者になる気はなかったはずの氏が、これほどまでに時間と労力、知力のすべてを費やしながらも続けてきた理由は何だろう。「翻訳をやっているときは夢中だし、たのしいですよ。それから聖書の翻訳にせよ、辞書批評にせよ、最近のアメリカ合衆国憲法(『アメリカ合衆国憲法を英文で読む』中公新書)の翻訳にせよ、わたしの仕事にはある種開拓者的なところがあったと思っています。どれも一種の義憤に燃えてやっているわけですが、そのじつ好きなものをやっているというたのしさがありますね」 わたしはドン・キホーテかな、錆びた槍で風車にぶつかっているようなものだから――そういって破顔一笑した飛田氏。1998年には大学を定年退職され、まとまった時間が取れるようになったという氏は、次にどんな冒険物語をわたしたちの前に披露してくれるのだろうか。※飛田茂雄さんは、2002年11月にご逝去されました。 インタビュアー:遠藤裕子(2001) |
