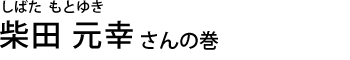  |
|
|||||||||||||||||
翻訳家ではありませんポール・オースター、スティーヴン・ミルハウザー、スティーヴ・エリクソンら、日本でも広く認知されたアメリカ人作家の訳者である柴田元幸さん。東京大学文学部助教授であることを知りつつ、つい“翻訳家”と呼びたくなってしまうが―― 「翻訳家ではないですよ。翻訳で食べていないという意味でね。仕事のうち8割の時間は大学教師として費やしていますから」 学期中に単行本の翻訳をする時間的な余裕はない。翻訳ができるのは長期休暇などの限られた時間だけだというが、「一日中やれるのなら1週間で1冊できる」と冗談めかすほど翻訳のスピードは速い。翻訳を「趣味、遊び」と軽く位置づけてしまえるのは、実際に本業があって、心から翻訳が好きなためでもある。抜きんでた英語力と翻訳力を前提としていることは言うまでもない。 本職は教師。正式には助教授だが、翻訳に対するのと同様、本業にも柴田さんなりの細かい定義がある。 「英文科の教師にはそれぞれの役割が何となく決まっています。一番上の層をさらに伸ばす人間も必要だけど、ぼくの役割は知的な中流階級を引っ張り上げることだと思う。むにゃむにゃの人を、むにゃむにゃよりちょっと良くするというか」 つまり、それまであまり読書をする機会のなかった学生を一段階引き上げるということらしい。学部でも優秀な学生にはついていけないと柴田さんは謙遜するが、そこでは情報提供をして方向性を示してあげるそうだ。 その「中流を引き上げる」という仕事が大学の外へ出たときに、それは“こむずかしい論文”ではなく海外の小説を翻訳で紹介するという形になって現れる。だが翻訳家(者)というくくりでアプローチされることには、居心地の悪さを感じる。 「翻訳者がこれだけ脚光を浴びるというのも、考えてみれば不思議ですね」 言われてみれば、もっともな意見である……。 成り行き人生翻訳者・柴田元幸の誕生となる記念すべき1冊目が何だったのか、質問を向けるとこう切り返された。 「原因があるから結果があると思われていますが、ほとんどの場合は結果から遡って原因を捏造しているだけ。これはニーチェの言ったことですが、ぼくもそう思います」 こういう動機やきっかけがあって今の自分がいる――そういうまとめ方に柴田さんは「生理的に抵抗を感じる」そうだ。学生時代の話をきいてみても、後の人生を決定づけるような“あの1冊、あの出来事”というものは出てこない。 「小中学生時代に本の虫でなくてもこういう仕事ができる、そういう例として受け取ってもらえるとうれしいですね」柴田さんは冗談でもなさそうに言う。 高校3年生の夏までは理系で物理や化学を選択していた。でも自分より理数系の科目に強い人間がたくさんいて「好きだけではついていけない」と感じ、大学での勉強も理系のほうが大変そうに見えて、文系に転向した。進路を考えたとき、官僚やサラリーマンになる気はなかったので法学部や経済学部は選択肢から消え、結果的に残った文学部を選ぶ。出願したのは東京大学文科三類(文学部・教育学部系)。国立ならば年間3万円程度の授業料ですむこと、自宅が東京だったこと、そして英語が得意だったことを踏まえての判断だった。 東大に合格したので併願していた外語大は受験しなかった。アメリカ文学を選んだのは、「イギリス文学の教授がほとんど授業してくれなかった」という単純な(ある意味で切実な)理由から。もし状況が反対だったら、イギリス文学を専攻していたという。 英文科に籍を置きながら英語が話せないのもどうかと思い、「1年もいれば話せるようになるだろう」と考え、3年生になる前に1年間イギリスへ遊学した(でも、そうはならなかった)。ゼミを受けていても、自分が文学に向いているとは少しも思えない。それでもとりあえず、1年間の自主留年をはさんで大学院へ進む。 「ぼくたちは、紛争世代の次にあたるモラトリアムの世代で、将来をはやくに決めたくないという人間がたくさんいたんです。好景気で職の心配もなかったし」 先延ばしのための進学。だが大学院で勉強をはじめると、遠く伸びた道がじつは枝分かれしていないらしいことがわかってくる。 「院に入ったら、あとは大学の教師をめざすのがとりあえず一番抵抗が少なく手っとり早い」 学部で6年、院で5年。11年のモラトリアムを経て、柴田さんは大学の先生になった。アメリカ文学の専門家であるため、次第に翻訳がらみの仕事も舞い込むようになり、そうした流れの中でポール・オースターの『幽霊たち』を訳出した。文芸翻訳書の第1冊目にあたるが、それを翻訳者・柴田元幸の誕生と見ることは“ウソっぽく”思えてしまう。「作業としては『鍵のかかった部屋』の方が先に出来上がっているし、それまでに訳した思想書(『デカルトからベイトソンへ』)だって意味ある仕事だし」 教師あるいは翻訳者という結果の、直接の原因にあたるものは確かに存在しない。言ってみれば、その場その場の小さな原因と結果が連鎖していって今がある。 それが、柴田さんが言うところの「成り行き人生」なのだろう。 はやさの秘密翻訳をするスピードは最初から速かった。控え目とも思える発言の多い柴田さんが「翻訳は速い」と断言するのだから、かなりのものであることは間違いない。そして、その速さの裏には柴田さんの翻訳理論も隠されている。 「意識して速くあろうともしているんです。ゆっくり訳すとどうしてもセンテンス単位で訳してしまうけれど、読者は文章の流れで読むわけだから、個々のセンテンスが自己完結していてはダメなんです。読むときの感覚、ノリを訳文で再現するためにも速く訳すべきで、速いから雑ということではないですよ」 第1稿はチラシの裏面を使っての手書き。それを奥さんにワープロで打ち込んでもらい、そこからじっくりと時間をかけ、読み直しや原文とのつきあわせといった練りの作業に移っていく。 訳文を練っていく上で、一番気をつけるのが読みやすさ。それは、いかに文章が読者の息づかいに馴染んでいるかだという。文章にも呼吸があることを“強烈に”感じたのは、大学院時代に三浦雅士さんの評論を読んだとき。それが柴田さんの文章作法の基礎になった。訳文に手を加えていくときにも、呼吸のリズムにどれだけ合わせられるかを考える。 伝えるべき情報は過不足なく正確であるのに、ひどく読みにくい訳文というのがある。それは語順に問題があったり、文章が長すぎたり切りすぎだったり、つまり「息づかいにあっていない」からだと柴田さんは指摘する。「人のこと言うのは簡単なんだけど」と間髪入れずにテンションを弛緩させるあたり、いかにも柴田さんらしいが、そうした文章への誠意や真剣な姿勢は、翻訳そのものへも向けられている。 柴田さんは翻訳が好きである。愛しているのだ。 愛について柴田さんは愛の人である。 『愛の見切り発車』、『むずかしい愛』という著書や訳書のタイトルもさることながら、このインタビューの時点で「愛の翻訳論へ向けて」という論文を執筆中だというから、“愛の人”と言い切ってしまっても差しつかえないだろう。
他者の訳書に対してはしばしば「愛情にみちた」という表現を使い、ご自身の訳書であるスチュアート・ダイベックの『シカゴ育ち』についても「いつにも増して愛着のある一冊」と評している。愛なくして、柴田さんの翻訳を語ることはできない。 「原文と張り合ったり、原文をばかにしたりして訳したものはやはり訳文に出ます。好きでもないものを訳すのは倫理的にまちがっている。愛情も敬意も持てないのに訳しては、テクストが可哀想ですよ」 「おこがましいけれど」と断った上で、柴田さんはミルハウザー、オースター、エリクソン、ユアグロー、ダイベック、ケイニンの6人を“ぼくの作家”としてあげてくれた。その“ぼくの作家”というのは、「長い目で見たらわからないけど、短い目で見た場合、少なくとも自分が訳したことで足はひっぱっていない」という意味合いだという。そのなかで、ことミルハウザーについては思い入れが強い。 「ぼくならこの人の気持ちがわかってあげられる、と言えますよ。オースターなら訳者によってそれぞれの味が出るでしょうけれど、ミルハウザーについてはぼくが訳すことで彼の味が出ているという思いはあります。妄想ですけどね」 柴田さんはあるエッセイの中で、原作者と翻訳者の関係を「主人と奴隷」のそれになぞらえているが、「主人と奴隷」という関係には屈折した愛のかたちも見え隠れする。奴隷は主人を思うあまり、「秘め事」を働くこともある。 「形容詞には“暗い”と“明るい”のように意味の上で両極があるわけですが、訳そうとする形容詞がその中間の意味でも、文脈から、あるいは日本語としての自然さから、などの理由でもっと片方寄りにしたほうがいいと判断すれば、そうします。だから、奴隷といっても不実な奴隷なんです」 翻訳という仕事がお金になるかと問われるのが一番厄介だと柴田さん。「遊びと思ってできないのならやめた方がいい」とまで言い切ってしまうそうだが、先日ある講演会で「そうはいっても、家計の足しにしようと思って翻訳を請け負っているのに、時給何十円では会社に騙されているとしか思えない」とひとりの主婦に言われ、ほとほと困ってしまったという。 「お金をもらえなくてもやるかもしれない、それぐらいの気持ちになったら翻訳をやればいいんです」という柴田さんの言葉を聞き、愛は無償なのだなと思う。 ドキュメント:ニューヨーク3部作刊行まで'86年頃から友人の翻訳を手伝ことを始めていたが、大学院時代の知人でアメリカ文学・映画研究者の畑中佳樹さんから誘われて村上春樹さんの翻訳原稿(『熊を放つ』)のチェックを一緒にすることになった。その本の担当編集者の一人がスーパーエディターこと安原顯さん。安原さんとの出会いによって、その後雑誌『マリ・クレール』で連載を持つようになり、アメリカ文学者・柴田元幸の名は出版市場に“流通”するようになった。 そんなおり、“新しいアメリカの小説”というシリーズを企画していた白水社の編集者平田紀之さんが、柴田さんに目をつける。 「お好きな作品を2つ訳してくれませんか」 そこで選んだのが、ひとつはミルハウザーのIn the Penny Arcade、もうひとつはオースターのニューヨーク3部作1作目にあたるCity of Glass。柴田さんは早速オースター作品の翻訳に取りかかったが(「当時は暇だった」)、すでに角川書店によって版権が取得されていることがわかり、20ページほど訳したところで柴田訳『ガラスの街』は幻と消えることになる。 そこで2作目にあたるGhostsに手を伸ばしかけるが、「オースター翻訳の1作目としては内容が抽象的すぎる」と判断(「結果的にその判断は間違っていた」)、わかりやすいThe Locked Roomを訳し始めた。 同じ頃に柴田さんが『マリ・クレール』でオースターを紹介すると、その記事を読んだ新潮社の編集者森田裕美子さんから連絡が入った。 「おもしろそうだからやりましょう」 こうして、残るGhostsの翻訳も決まった。 最初に訳が上がったのは白水社刊となる『鍵のかかった部屋』。だがシリーズで出すうちの1作なので、他の人の翻訳が出来るまで刊行されない。結局、『幽霊たち』が先に出ることになる。すると「うちのが1作目」と角川書店も動いた。 89年春、『シティ・オヴ・グラス』角川書店より刊行。 同年夏、『幽霊たち』新潮社より刊行。 同年秋、『鍵のかかった部屋』白水社より刊行。 ニューヨーク3部作は、こうして無事に原書の発表順どおり、日本の読者に紹介されたのである。 生半可な学者「ぼくは大田区の蒲田という、ぜんぜんメインストリームの文化のないところに育った。中途半端な下町文化はあっても、大学でやるようなメインストリームの文化とは程遠いところにある場所です。 つまり文化的なりあがりとして、こういうところ(東京大学)で教師をやっているわけですよ。メインストリームの真ん中に立って、ストレートに大学教師を演ずることはぼくにはできないと思う。どう見たって、大学教師のパロディになってしまう。まあそこに自分の存在意義があるんだろうなとも思う。 パロディといっても、権威をコケにするということではなくて、違った視点から教師をするという意味です。中流を引き上げるというのもそこに繋がります。 正当ではないから生半可な學者。でもいつまでもその看板をぶら下げているのも不健全かなと思って、それで駒場から本郷のキャンパスに移ることにしたんです。駒場が周縁だとすれば、本郷は中心ですからね。 そうはいっても、ここに来れば自分を周縁的な立場に置くようになるよね。少なくともそう自己規定してしまう。こちらにも何人もの教師がいるわけで、そのなかで自分はやっぱり周縁かな、と」 (“アカデミックな堅苦しさは嫌いですか”の問いに対して。「『堅苦しさ』という言葉のなかにはすでに否定的なニュアンスがあるから、それを好きだっていう人はいないよね」という絶妙の返しに続いてのコメント) “柴田元幸”の商品価値初期オースター作品の翻訳エピソードを窺っているとき、柴田さんはご自身の名が雑誌などの媒体で広まることを「流通」と表現した。本業の職場である大学から飛び出した“柴田元幸”に対しては、客観的な見方をしているようだ。 「翻訳者としての自分に商品価値があるとしたら、翻訳の勉強だけをした人にはない知識がある、というところ。そこが大きいと思いたいですね」 駒場キャンパスで毎年1学期間、翻訳のワークショップを行なっているが、学生からの「翻訳家になるにはどうしたらいいですか」という質問には「翻訳家になろうと思うな」と答えているそうだ。それは学者になろうと思って大学院で勉強した自身の経験が、結果的に翻訳に役立ち、翻訳者としての価値を生んでいるという実感があるからだ。 「英語を細かく読むトレーニングを受けたから、村上春樹さんのようなものすごく翻訳の上手な人の訳文をチェックする機会に恵まれた。そのときに訳し方を学べたし盗むこともできた。ラッキーだったと思いますよ」 柴田さんの訳書は最低でも4千部ぐらいは売れる。それは「自分の訳文を好意的に受けとめてくれる読者が多い」からでもあるが、こうした受け入れられ方がいつまでも続くとは思っていない。 「今の時代にあった訳というのは、次の時代には受け入れられないということかもしれない。だから自分の需要が、将来も当然あるものとしては考えていません。高校生に受け入れてもらえると、次の時代くらいはまだイケるかなって思うけど(笑)」 では、肝心の翻訳される素材である文学は今後どうなっていくのだろう。文学翻訳の今後を訊ねると、「横浜ベイスターズの10年後がどうなっているのかという質問と同じくらいわかりませんね」と考え込んでから、こう話してくれた。 「メディアが増え、書物の割合がどんどん小さくなっていくことは間違いないでしょう。小説を教養のために読まなければというプレッシャーはなくなり、好きな人が好きなだけ読むという方向に進むかも知れない。その意味では健在です。でも高度資本主義の時代だから、本であれ何であれ商品にならないと消えてしまうというところがつらい。アメリカ文学は今のところ辛うじて商品として成立していますけど、今後はわからないですね」 ただ、外国の小説を読む必要がないという流れにはなりそうにないという。学ばなければという強迫観念がなくなったかわりに、外国・日本を問わず同じ商品の対象になると柴田さんは見ている。 商品といえば、売れっ子翻訳者“柴田元幸”のブランドを冠したアンソロジーは好セールスが見込めそうに思えるが―― 「そう思われているようですけれど、アンソロジーはすごく苦戦しているんです。でもオースターの訳書は売れる。ある意味では、そうした状況に安心しますけどね。訳者じゃなくて、作家で売れるというのは」 口述筆記はあるか?翻訳は今後も続けていこうと考えている。 すでに日本での地位を確立した作家については、自分がやらなくても訳されるだろうから、無名の作家を訳していきたいし、その方が意義があると感じている。そう思えるのも、専業の翻訳家ではなく好きで翻訳をしているからこそ。だが、現実にはそううまく行きそうにない。 「著者と訳者をセットで考えている読者が多いんですよね。オースターなら柴田、という図式ができているみたいで、もし別な人が訳すことになればやりにくいだろうと思うんですよ。もちろんオースターは好きな作家ですから訳すことに問題はないんだけれども、ほかに新しい作家も訳したいし、でも相変わらず1日は24時間しかないので、そこが一番困る」 今まで以上に翻訳のスピードを上げるには口述筆記しかない、というとんでもない解決案も飛び出した。柴田さんがレコーダーに手を伸ばす日も来ないとは限らない。 「でも手書きで1字1字書いていくのと違って、ナルシシズムに浸る快感はなさそうだから、たぶんやらない(笑)」 “遊びでやっている”という翻訳に向ける情熱には、すさまじいものがある。多忙を極めながらも、新しい作家を訳していこうという姿勢は生半可からは程遠いし、とてつもない使命感さえ感じさせる。その誠意が、アメリカ文学者であり翻訳者である“柴田元幸”の広い流通につながっているのだろう。 老後は「春と秋は東京、夏はロンドン、冬はメルボルン(つまり冬といっても涼しい夏)」で過ごしたいという。丸1年、翻訳にあてられる時間を得た柴田老人は、レコーダー片手に喋り続ける日々をおくっているかもしれないし、いないかもしれない。あるいは、まったく違うことをしているのかも。 成り行きは、さて? インタビュアー:金田修宏(2000/4/18) |

