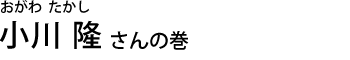  |
| |||||||||||||||||
3つの顔を使い分ける小川さんは翻訳家、編集者、そして学校講師という3つの顔を持っている。いわゆる、兼業翻訳家である。 兼業翻訳家であること自体はともかく、小川さんくらい様々な仕事を抱え込んでいる翻訳家もめずらしい。2つの学校で翻訳を教えつつ、週に2、3日を編集の仕事に費やし、それでいて年に2冊のペースでコンスタントに訳書を出している。傍目に見ると、実にバランス良く仕事を回転させているように見えるが、小川さん自身は、たまたまこうなっただけのこと、といって笑う。
「ぼくは、他ではつぶしがきかなくて、しかたなくなった翻訳家なんです。編集の仕事も引き止められるまま続けていて、学校の講師も誘われて断らずにやっているだけで」 ちなみに、それぞれの作業にかける時間もほぼ均等だとのこと。こうなると失礼ながら、いったいどれが本業なのか分かりにくくなってしまう。だが、ご本人によれば、あくまでも中心になるのは翻訳であり、職業は「翻訳家」だと言い切る。 いつも周りに本があったそんな小川さんは、やはり子供の頃から読書好きではあった。 「幼稚園くらいから本の虫でしたね。最初はミステリでした。『少年探偵団』から入って、ホームズとかアガサ・クリスティ。中学に上がった頃には、哲学とか、そういう難しい本を背伸びして手を出したり。あとは、家に全集がいくつかあったので、次第にそこから選んで読むようになりました」 高校までは、特にジャンルを限定せず、目につくものを片っぱしから読んでいた。いわば濫読派である。それでも、本を読むということを特に意識することはなかった。 「周囲がもう、読書をすることが当たり前という感じで、友だちともよく本の話をしていた」 だからといって、本好きの友人ばかりだったわけでもない。本を読むということが特別なものではなく、ごく日常的な行為だった。じっさい、小川さん自身も読書に熱中していたという記憶はないという。むしろ夢中になったのは音楽だった。 「ぼくは典型的なビートルズ世代なんです。姉がもともとアメリカのポップスをよく聴いていたので、そこから入ったんですが、ビートルズが出てきたことで一気に惹きつけられてしまった」 何がそんなに魅力的だったのか。小川さんによれば、それは圧倒的なリアリティだった。それまでのポップスといえば、大人が子供に向けて作ったものという印象があったが、ビートルズはまったく違っていた。歌詞もサウンドも、まったく同世代の生々しさにあふれていた。 「たとえば初期のビートルズなんて、あの子と手をつなぎたいとか、ぼくたちにとって本当に身近な気持ちを歌にしていた」 そうした率直なところに、たまらなく惹かれていったのだという。 アルバイトに明け暮れた日々音楽にのめり込む一方で、生活の一部として読書を続けていた小川さんだったが、それでも読書傾向というものが現れつつあった。それを意識するようになったのが、大学進学の頃だった。当時関心があったのは、カート・ヴォネガットなどの現代アメリカ文学、それからフランスのシュルレアリスムだったという。 結局、小川さんは仏文科を選んだ。フランス語の詩を原文で読んでみたいから、というのがその動機だったが、実際にはそのような勉強はほとんどできないままだった。 「入ったとたんに、大学のロックアウトや自治会のストなどが続いたので、授業が満足に継続されたことはなかったですね」 学生時代はもっぱら、音楽やアルバイトで暮らしていた。いちおう卒業はしたものの、特に就職活動はせず、そのままの生活を続けた。 「いろんなことをやりましたが、長かったのは倉庫や工場での仕事。中二階や大きな棚を組み立てるというものでしたが、最初に手順を考えてから動くようにしていたので、頭脳労働で補う肉体労働という感じでした。それにギャラがとても良かったので、ついつい就職もしないままで」 仕事が楽になるということで周囲にも喜ばれ、最終的には全体を取り仕切る、請負業者のような立場にまでなったという。長く続けたかった仕事だったが、終わりは突然にやってきた。 「石油ショックで、一気に仕事がなくなってしまったんです」 ふたたびアルバイトを掛け持ちでこなす生活に戻ったが、その中に、洋書の下読みという仕事があった。いわゆるリーディングである。 「とりあえず編集の仕事がしてみたいと思っていたのですが、不況でなかなか見つからなくて。英語が出来る人間を探しているところがあると知人から教えられたので、話を聞きにいったら、洋書を渡されて、内容をまとめてほしいと言われたのです」 そこは翻訳書を中心に手掛けていた編集プロダクションだった。仏文科ではあったが、ロックに親しんでいた小川さんは英語も読みこなせるようになっていた。 「大学に入った頃から、なかなか翻訳されない海外SFを原書で読んだりするようになっていました。自信がついたのが『指輪物語』を読んだ時でしたね。最初の巻だけ翻訳になってて、なかなか続きが出ないので、ペーパーバックを買ってきて。最初は厚い本だなあと思ったんですが、あっという間に読めたんです。それが原書を日常的に読むようになったきっかけですね」 言われるままにリーディングを続けていたが、しばらくすると、社内事情から語学のできる人間が欲しいということで、週に何日か通うことになる。仕事は多岐に渡った。これまでの仕事に加え、新刊洋書のチェックや翻訳書の企画も手伝うようになり、また社内で発生する海外との折衝も担当した。 こうして、大量に出版される洋書と格闘する日々が始まった。この時、小川さんは29歳になっていた。 誘われて翻訳の道へ仕事としてひたすら洋書を読む日々が続いたが、そのうち新しい企画に編集者として参加することになった。ある出版社が海外SFのシリーズを立ち上げることが決まり、小川さんも関わることになったのだ。ちょうど海外のSF情報誌の購読手続きを取ろうとしていた時期とも重なる、タイミングの良さだった。 それからしばらくして、自宅に不思議な手紙が届いた。翻訳家の小隅黎(柴野拓美)さんからだった。当時小隅さんは、小川さんが購読した情報誌の日本側エージェントを務めていた。 「今はぼくが、小隅さんから引き継いで、その雑誌のエージェントになっているので分かるのですが、新規の申し込みがあると、どういう人なのか気になったりするものなんです。ぼくの場合も、そういうことでご連絡されてきたようでした」 小隅さんといえば、星新一など数々の作家・翻訳家を輩出した、日本初のSF同人誌『宇宙塵』の発行人であり、後進の指導にも熱心なことで知られている。小川さんも自然と、同人にならないかと勧誘を受けた。 「その時に、翻訳をやりたいのかと訊かれたんですね。出版社に正採用を断られたことがあって、それからはずっと翻訳家として食べていければいいなと思っていたのを察してくれたのです。それで、それまで試しに訳していた短編を送ってみたところ、思いがけないことに、すぐ採用された」 また、その少し前から、編集の仕事を通じて紹介された、あるベテラン翻訳家の依頼で、下訳も何冊かこなしている。 「下訳ではいわゆる冒険小説が多かったのですが、とても勉強になりました。基本的にエンタテインメントというのはプロットなんです。SFだとやっぱりディテールで読み込ませるようなところ、少しリズムが悪くならなきゃいけないところがあって、そういうところはじっくり読むんでペースが変わってしまうけど、エンタテインメントはひたすらスピードを出さないといけない。おかげで、ずいぶん翻訳が速くなったと思います」 仕事で翻訳ができるとは思っていなかったものの、翻訳に取り組んでいたのは学生時代からだった。 「原書で読んでいたSFなんかを訳していましたね。昔からロックの歌詞とかを訳してたんで、読んで面白かったのは訳してみようっていう習慣はあったんです」 新刊洋書の紹介を始める仕事の関係から、SFに本格的に関わるようになった小川さんだったが、すぐにあることに気づく。 「『宇宙塵』の例会にお誘いしていただいてから、SFファンの集まりに出るようになったんですが、原書を読んでいる人があまりいなかったんですね。その頃、関西では洋書の新刊を紹介するっていう活動がさかんだったんですが、関東にはないと言われて。それで、せっかく新しい本を読んでいるのだからということで、自分で始めたんです」 小川さんはSFファンの集まりで、新刊洋書のレビューを載せた通信紙を配るようになる。当初はひとりで始めた活動だったが、自然と周囲に人が集まっていった。その多くは、SFや幻想文学に興味を寄せる大学生だった。集まり自体も「ぱらんてぃあ」という名前のファングループとなり、山岸真さんを筆頭に、多くの翻訳家・評論家を生み出している。 また「ぱらんてぃあ」を通じて、SFファンとの交流を深めたことで、交友範囲はどんどん広がっていった。小川さんにとって初めての訳書も、そうした付き合いから生まれている。 「知り合いだった関西のSFファンが、大学を出て編集者になったんです。その彼から連絡があって、SF映画のノベライゼーションを翻訳してみないかと声を掛けられた」 ちなみにこの時の編集者が、現在は翻訳家として活躍する大森望さんである。 紹介者としての顔〜サイバーパンクとの出会い訳書を出す前から、小川さんは商業誌に原稿を書くようになっていた。新刊洋書のレビューを中心に、社会状況の変化を折り込みながら海外SFの最新の動向を伝えるという、いわば紹介者的な仕事である。 「SFでは、新しいものへの関心がことのほか強いので、新刊を読んであれこれ話す人間というのはわりと重宝されるんです」 常に海外の状況に接してきた小川さんには、まさしくうってつけの仕事だった。そもそも、SFでは翻訳家が紹介者を兼ねるという伝統もある。ただし小川さんには、それまでの紹介者とは違った一面があった。気に入った作家には、積極的に会いに行ってしまうのである。SF作家、ブルース・スターリングとの親交もそうして始まった。 80年代といえば、未来指向が再び強くなった時代でもある。コンピュータを始めとするハイテク・ブームに、映画『ブレードランナー』。そしてSFでは、サイバーパンクという大きな動きがあった。小川さんは、その中心人物と古くから交流のあった唯一の日本人だが、それもふとしたきっかけから始まっている。 「好きな作家にハーラン・エリスンという人がいたんですが、その彼が発掘した新人作家というふれこみのシリーズがあったんです。その中に、とても面白い作品があった」 それはブルース・スターリングという、まだ20代の青年作家のデビュー作だった。続いて出た2作目にも感銘を受けた小川さんは、 「彼に手紙を出したんです。すると、折り返し届いたのが、スターリングが出していたニューズレターだった」 それは『チープ・トゥルース』(安っぽい真実)というタイトルの文書で、スターリングが周囲の作家仲間と共同で出していたものだった。そこでは、ロックやポップカルチャーで使われるスラングをまじえつつ、SF業界の動向がひたすら挑発的に取り上げられていた。 「『チープ・トゥルース』を読んで、これは面白いと思ったんですが、よくよく見てみると、スターリングの他にも、気に入っていた新人作家がのきなみ関わっていた。これは面白そうだから、ちょっと見に行ってみよう、と」 いくら気に入っていたとはいえ、当時のスターリングはまだ著書数冊の、星の数ほどいる新人作家のひとりに過ぎなかったわけで、小川さんのいれこみぐあいは相当のものだったといえる。 「手紙を出して、行ってもいいかといったら、みんなで歓迎すると。彼は、当時日本の音楽に興味を持っていたんです。日本のロックのレコードをなぜか持っていて、面白がっていた。向こうでは入手が難しいものですから、日本からレコードをいくつか持っていきました」 ロサンゼルスで行われた世界SF大会に参加した後、小川さんはスターリングの住むテキサスへと向かった。小川さんの第一印象はというと、 「それほど年は違わないのですが、とにかく言うことが若いのにびっくりしましたね。一世代下という感じで」 だがロックを始めとする大衆文化に深い理解を寄せ、時事的な問題にも関心を持つなど、共通点の多いふたりはたちまち意気投合する。 「まず話したのが、新しく出てくる作品がどうも面白くないということでした。売れている作品といえば、ひたすら長いだけのサイエンス・ファンタシイが多かったし、評価の高い作家たちにしても、変にヒューマニズム指向だったり。全体として、世の中の変化についていけてないような印象があった。他にも色々とSF以外の世界ではおもしろい動きがあるのにと、残念な気がしていたんですが、そうした認識でも一致していたんです」 当時のスターリングは、作家同士で集まっては作品の合評会を開いており、小川さんはそうした活動にも興味をもった。 「とにかく調べるということをたたき込まれていましたね。面白いアイデアを思いついても、それをすぐに書いてしまったりはしない。当時は昆虫をモチーフにした作品を書いていましたが、何を取り上げるにもかならず資料にあたって、徹底的に調べていました。イスラム原理主義によるハイテク革命への機関誌みたいなものまで読んでいて、感心させられました」 それから数年してサイバーパンクが本格的に注目されるようになるのだが、その中心にいたのが誰あろう、スターリングだった。ウィリアム・ギブスンなど仲間の作家たちと組んでは運動を盛り上げ、スポークスマンとしてマスコミ相手に熱弁をふるった。 一方で小川さんの所にも、来日した作家の案内から、サイバーパンクに関する講演依頼まで舞い込んできたという。そんな中で面白かったのが、それまでのSFファンとは異なる層にアピールしたということだった。 「ロック・ミュージシャンとか、前衛芸術のアーティストとか、そういう人たちが関心を寄せてくれていた。これは世界的な傾向なのですが」 スターリングとは今でも親しくしている。日本で発表された作品はほとんど小川さんが訳しているほか、2年前にオーストラリアで開催された世界SF大会では、代役としてステージに上がり、SFで最もメジャーな賞とされるヒューゴー賞を受け取った。 現行版『スキズマトリックス』のペーパーバックには、作者によるまえがきが新たに収録されている。そこには「この本が日本で出ると、すかさず増刷の知らせが届いた。以来ぼくは、あの国の読者に対して揺るぎない信頼を抱いている」とあるが、そこに小川さんの翻訳が大いに貢献していることは言うまでもないだろう。 翻訳を教えるということ10年ほど前からは、翻訳を教えることも始めた。 「すでに講師をやっていた翻訳家の人から誘われたのです。SFをやってもいいですかと聞いたら、かまわないといわれたので(笑)」 とはいっても、授業の課題にSFを使うことはほとんどない。必ずといっていいほどアメリカの一般小説、それも新作を取り上げている。いわゆるジャンル小説では専門知識が必要になることが多いため、課題としては不適切だというのは分かるが、それにしても、なぜ新作なのだろう。 「これからプロの翻訳家として出ていく人が、昔の作品を訳す機会ってそれほどないと思うんですよ。読者としてなら、古典を読むというのは分かるんですが。そもそも翻訳を仕事にしていきたいという人は、昔のものを訳したいとは思っていないんじゃないでしょうか。ぼく自身、新しいものに関心があったから、この仕事を始めたようなものですし」 翻訳の講座の他にも、リーディングの講座も受け持っている。 「とにかく本の話をするのが好きなので、リーディングの授業なら語学的なことを言わなくていいから、その分もっと本の話ができるじゃないか、と思って(笑)。すごい読み違えをする人もたまにいますけど、それもまた新鮮だし」 編集者として翻訳書の企画を主に担当している小川さんは、機会をみては翻訳学校の生徒にも翻訳やリーディングを依頼している。 「もうちょっと読書量が増えればうまくなりそうだな、という人にはお願いしています。やはり仕事ですから、出来ない人にやってもらうわけにはいかないのですが」 とにかく「新しもの好き」「ぼくはとにかく、新しいものが好きなんです」 この言葉に、小川さんのこれまでの道のりが集約されているといえる。 小川さんの意識は、常に次代に向けられている。ひたすら新刊洋書を読み込み、海外の出版情報を収集する。興味深い動きがあれば、いち早く周囲に知らせる。それは仕事だからというより、好きなことを仕事にしたというのが正しい。その多彩な活動も、「新しいものへの指向」というキーワードでくくれば、ひとつのまとまりとして捉えることができる。 取材当日、小川さんは書斎の整理中だった。壁を覆いつくすように置かれた書棚には、膨大な数の原書に加え、数十年分もの洋雑誌のバックナンバーが並んでいる。 「これは、今日届いた分ですね」 そう言われてみると、十数冊の洋書が床に置かれていた。 人と話をするのが好きという小川さんは、毎年の旅行も欠かさない。海外のSF系イベントに取材を兼ねて出かけるほか、昨年はイタリア、今年はシンガポールに行ってきた。 翻訳に専念することも考えたりします、という小川さんだが、そうはいっても誘いには弱い。 「面白そうな話なら、すぐに乗ってしまいますね」 小川さんの多忙な日々は、まだまだ終りそうにない。 ここでも小川さんのインタビューが読めます インタビュアー:寺町徹(2000/11/14) |
